トピックス
-
2025.4.11(最終更新日:2025.4.28)
<施工管理>防犯カメラ工事を安全に実施するために

ここでは、電気・電気通信通信工事施工管理技士試験にも出題される、安全管理の基準について解説します。
電気・電気通信工事施工管理技士は国土交通大臣の指定機関が実施する国家試験の合格者に与えられる国家資格です。電気/電気通信工事施工管理技士には、工事の現場で施工計画・工程管理・安全管理・技術者の監督などの施工管理に関わる幅広い知識が求められます。
防犯カメラ工事の安全管理
防犯カメラの工事現場を実施するにあたり、労働災害を防止し安全に施工を行うために様々な活動を行っています。
・危険予知活動(KY活動)
・指差し呼称
・4S活動(整理・整頓・清掃・清潔+しつけで5S活動)
・ツールボックスミーティング(作業単位で行うMTG)
電気・電気通信工事の安全基準
高所での作業の落下事故や電気工事での漏電や感電等、防犯カメラ工事の際も危険なポイントが多数あり、安全基準について労働安全衛生規制に細かく定められています。
高所作業車の安全基準の例
・作業計画、作業指揮者、作業時の合図を定め、関係労働者に周知する
・1か月以内毎の定期自主検査を行う(3年間の記録保存)電気工事に関する安全基準の例
・対地電圧150V超の電動機械を使用する際は、感電防止漏電遮断装置を接続する
・感電の危険がある場合は、労働者に絶縁保護具を着用させる
・漏電遮断装置は、使用開始前に点検をする
・感電防止のための絶縁覆いは毎月1回以上点検する
・絶縁保護具は6か月以内毎に点検する(3年間の記録保存)墜落・落下防止に関する安全基準の例
・高さ・深さ1.5m以上で作業するときは、昇降設備を設ける
・高さ2m以上で作業するときは、作業床を設け開口部に墜落防止のため囲いを設置する(作業床のすき間は3cm以下、幅は40cm以上)
※作業床を設けることが著しく困難な場合は、防網を張り、かつ安全帯を使用する。
・脚立は、脚と水平面の角度が75度のものを使用する
・移動はしごは、幅が30cm以上のものを使用する
・踏み抜く可能性がある屋根で作業するときは、幅30cm以上の歩み板を設ける
※昇降設備は1.5m、作業床は2m通路に関する安全基準の例
・通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かない
・架設通路の勾配は30度以下として、15度を超えるものには滑り止めを設ける、高さ85cmはしごに関する安全基準の例
・はしごの上端を床から60cm以上突出させる
停電作業に関する安全基準の例
・開路に用いた開閉器に、作業中に施錠し、または開閉器に通電禁止する表示し、または監視人を配置する。(通電禁止表示すれば監視人の配置は省略できる)

・開路した電路が高圧または特別高圧の場合は、検電器具により停電を確認し、短絡接地器具により確実に短絡接地する。
短絡接地とは
停電作業中に誤通電や他の電路との混触を防ぐための安全対策のことで、電線と地面をつなぐ接地で、短絡接地金具や短絡接地器具を用いて行われます。
参考「一般社団法人安全衛生マネジメント協会 HP」
・開路した電路が電源ケーブル、電力コンデンサ等を有する電路で、残留電荷による危険がある場合は、安全な方法で残留電荷を確実に放電する。
残留電荷とは
ケーブルやコンデンサを停電させた場合、そのままでは電荷が残ります。作業場危険な場合があるため、放電コイルや放電装置等を使って放電させる必要があります。・開路した電路に再度通電する際は、感電の危険が生ずる恐れのないことと、短絡接地器具を取り外したことを確認する。
感電防止措置関する安全基準の例
・低圧の充電電路に近接する場所で電路や支持物の敷設等の電気工事を行う場合で、感電の危険がある場合は、充電電路に絶縁用防具を装着させ、又は活線作業用器具を使用しなければならない。

・移動電線に接続する手持型の電灯、仮設配線や移動電線に接続する架空吊り下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険や電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。

・充電された架空配線に近接して移動式クレーンを使用する作業があるときは、架空配線を移設する。
・電気室などの区画された場所で、電気取扱者以外の立ち入りを禁止をした場合は、充電部分の絶縁覆いを省略できる。
掘削作業に関する安全基準の例
・掘削機械、積込機械、運搬機械の使用によって、ガス導管や地中電線路などの損壊により危険がある場合は、これらの機械は使用せず手作業する。
・地山の掘削作業を実施するときは、掘削作業主任者に、要求性能墜落静止用器具や保護帽の使用状況を監視させなければならない。
・手掘りにより砂の地山の掘削を行う場合、掘削面の勾配を35度以下とし、または掘削面の高さを5m未満とする。
・土止支保工を設けた時は、設置後7日を超えない期間ごとに点検しなければならない。
土止支保工とは
地下構造物などの築造に伴う掘削作業の際に土砂の崩落を防ぐために設けるものガス等の容器の取り扱いに関する安全基準の例
・ガス溶接等の業務に使用するガス等の容器については、通風又は換気の不十分な場所(気密性の高い場所)で設置、使用、貯蔵、放置してはならない。
・使用前、使用中の容器とその他の容器の区別を明らかにする。
・容器の温度を40℃以下に保ち、運搬時はキャップを施す。
玉掛作業に関する安全基準の例
・ワイヤーロープの安全荷重は、つり角度によって変わる。
・玉掛作業は、その日の作業開始前にワイヤーロープの異常の有無について点検を行う。
・エンドレスでないワイヤーロープまたは吊りチェーンについては、その両端にフック、シャックル、リングまたはアイ(輪)を備えているものではなくてはいけない。
・ワイヤーロープの安全係数は6以上でなければならない。

作業別の安全基準
項目 注意点 危険
作業投下 高さ3m以上からの投下は投下設備と監視人の配置 飛来・落下 物体の飛来・落下は禁止(合図者の有無に関わらず) 酸素欠乏 空気中の酸素濃度が18%未満の環境を酸素欠乏という マンホール・ピット内作業では作業主任者が必要 作業
場所作業床 高さ2m以上の作業場所に設ける 作業床幅40cm以上(狭小な場所、つり足場等を除く)、すき間3cm以下 作業床の手すり高さ85cm以上 作業床がわく組足場の場合、幅木高さ15cm以上 その他足場の場合、幅木高さ10cm以上 折りたたみ式脚立 脚角度75度+固定金具 移動はしご 幅30cm以上+すべり止め 歩み板 屋根作業時には幅30cm以上の歩み板を設け、防網を張る 高所作業車 1か月以内毎の定期自主検査を行う(3年間の記録保存) 安全衛生キーワード

作業場の安全衛生を促進し、労働災害を防止し、安全に工事を完了するには、様々な取り組みがありますが、そのひとつに安全衛生に関する標語やキーワードを共有することがあります。「安全第一」「安全、ヨシ!」などの標語は、作業中の注意喚起を促し、全員が安全に対する意識を高める助けになり、事故のリスクを減少させることができます。
ここでは労働災害防止・安全衛生促進のための安全キーワードについて解説します。
キーワード 説明 TBM
(ツールボックスミーティング)作業前の短い時間で職長を中心に作業チーム全員が安全作業について話し合う安全教育 新規入場者教育 新しく作業場に入場する作業員に対し、事業者が作業員の経験や技術力をふまえたうえで作業場特有のルールや慣習について指導する安全教育 安全管理者の職務 朝礼、4S運動、TBMなど労働者に対する安全教育を行う 4S運動 「整理」「整頓」「清潔」「清掃」の頭文字を取ったもので、職場環境の整備により安全衛生を促進する運動 KYK(危険予知活動) 危険作業に従事するにあたり、テーマを定め、どのような危険が潜んでいるか話し合うことで安全衛生を促進する運動 オアシス運動 「おはよう」「ありがとう」「失礼します」「すみません」の頭文字を取って名付けられた、コミュニケーションを図ることで現場の安全衛生を促進する運動 ヒヤリハット運動 ヒヤリとしてハッとしたものの、重大な労働災害には至らなかった事象を取り上げて、労働災害の原因を取り除く運動 安全パトロール 事業所や単位作業場を巡回し、危険個所や危険作業がないか定期的に確認し労働災害の原因を取り除く運動 COHSMS(コスモス) 建設業者がPDCAサイクルにより自主的かつ継続的に安全衛生を促進するための仕組み 安全施工サイクル 毎日、毎週、毎月の安全衛生管理上の基本事項を定型化、習慣化したもの ハインリッヒの法則 1件の重大な労働災害の影には、29の軽微な事故が隠れており、その背景には300件もの以上が隠れているという法則 熱中症の手当 塩分を含んだ水分を飲ませる。意識が混濁したり水分が摂取できない場合には直ちに救急搬送の手配をする 熱中症の予防 多量の発汗を伴うことが予測される作業場においては、作業者が定期的かつ容易に補給できるよう塩及び飲料水を配備する このほかにも、安全衛生管理に関するキーワードや標語は多数あります。共通の標語を作業員で共有することは、労働災害防止のために非常に効果的です。安全な職場を実現するためには、標語やワードを積極的に活用し、全員で協力して安全を守る意識を高めていくことが求められます。
安全衛生管理を徹底して工事実施致しておりますので、防犯工事のご依頼もご安心してお任せください。
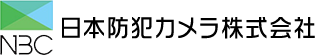
 03-6264-2138
03-6264-2138







