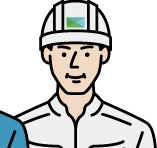トピックス
-
2024.8.3(最終更新日:2025.4.28)
<施工管理>電気通信工事施工管理上の留意点

ここでは、電気通信工事施工管理技士試験にも出題される、各工事・作業においての施工管理上の留意点について解説します。
電気通信工事施工管理技士は国土交通大臣の指定機関が実施する国家試験の合格者に与えられる国家資格です。電気通信工事施工管理技士には、電気通信工事の現場で施工計画・工程管理・安全管理・技術者の監督など電気通信工事の施工管理に関わる幅広い知識が求められます。
ケーブル配線の施工管理上の留意点
「電線」や「ケーブル」とは有線電気通信を行うための導体のことで、代表的なものとしては、低圧ケーブル、光ケーブル、UTPケーブルがあります。強電流電線は含まれません。
ダクトや線ぴ配線時の施工管理上の留意点
ダクト内配線
通線は、ダクト内を清掃した後に行い、ダクトのふたには電線などの荷重がかからないようにする。
金属ダクト・バスダクト
ダクト相互やダクトと配分電盤、プルボックスなどの間は、完全に突合せてボルトなどにより接続する。
 バスダクトとは、アルミニウムや銅の導体を絶縁物で覆い、鋼板のケースに収めたダクトのことです。BUSBER(導体)+DUCT(ダクト)で「バスダクト」と呼ばれます。
バスダクトとは、アルミニウムや銅の導体を絶縁物で覆い、鋼板のケースに収めたダクトのことです。BUSBER(導体)+DUCT(ダクト)で「バスダクト」と呼ばれます。ライティングダクトの施工
・ライティングダクトを支持する際の支持点間隔は、2m以下となるようにしなければならない。
フロアダクトの施工(床下線ぴ工事)
フロアダクト相互、フロアダクトとボックスは堅ろうに接続し、電気的に完全に接続する。「一種金属線ぴ(メタルモール)・二種金属線ぴ(レースウェイ)の施工」
・線ぴを支持する際の支持点間隔は1.5m以下になるようにしなければならない。
メタル通信ケーブル配線の施工管理上の留意点
メタル通信ケーブルとは、銅やアルミニウムなどの電気信号を伝送する金属の導体をプラスチック材料等で絶縁した通信線を集合し、シースを施したケーブルのことです。ここでは、メタル通信ケーブルの種類によってどのような施工管理上の留意点があるか解説します。
UTPケーブルの施工
延長100mを超えて敷設しない。
UTPケーブルの端末処理
ケーブルの成端作業時、対のより戻し長は最小とする。
高周波同軸ケーブルの接続
ケーブルの相互接続と端末への接続は、高周波同軸コネクタを用いて行う。
電線相互の接続
合成樹脂製可とう電線管や硬質ビニル管、金属管、金属製可とう電線管の内部では接続や分岐をしない。
弱電ケーブルの端末処理
弱電ケーブルの端末処理は、くし形または扇形に編み上げの上、端末に成端する。
光ファイバケーブルの管路への敷設
・通線確認試験を行う場合には、事前にメッセンジャー等で線通しを行い、引き続き通線確認用テストケーブルを通す。
光ファイバケーブルの心線接続
・接続は、ほこりと湿気を避け、作業環境に応じテントの中で行う。機材、工具、材料を地面や床面に置かないよう、簡易作業台で作業する。
光ファイバケーブルのコネクタ接続
・コネクタ相互が半刺しにならないようにカチッと音がする等により最後まで挿入したことを確認する。
光ファイバケーブルのOTDR(光パルス試験器)の測定
・光ファイバ上の任意の位置の「反射光の強さ」を測るので、接続損失や急な曲げによる損失を個々に知ることができる。
光ファイバケーブルの挿入損失法
・光源から出た光を励振器(れいしんき)に入射させ、その出射端での「光の強度」と、さらに被測定光ファイバを通過して出射された「光の強度」の差から被測定光ファイバの損失を測定する。
光ファイバケーブルのカットバック法(切断法)
・入射端から1~2m離れた地点で切断した末端地点の「光の強度」と、切断前の光ファイバから出射される「光の強度」を比較して損失を測定する。
露出配線・転がし配線
・露出配線のケーブルの接続は、合成樹脂モールド工法やボックス内配線とする。
地中管路内への通信ケーブル配線
・管内にケーブルを敷設する場合は、引き入れに先立ち管内を清掃し、ケーブルを損傷しないように管路口を保護した後、丁寧に引き入れる。
二重天井内配線
支持具、支持材等を用い、ケーブル被膜を損傷しないように造営材等に固定する。ケーブルの支持間隔は2m以下とする。
 二重天井とは、上の階のスラブ(構造床)から離して、空間を空けて天井仕上げ材を張る二重構造の天井のことです。
二重天井とは、上の階のスラブ(構造床)から離して、空間を空けて天井仕上げ材を張る二重構造の天井のことです。床上配線
カーペット敷の場合は、カーペットの下に転がし配線をする。
平型保護層配線
床面を清掃し、付着物を取り除いた後に敷設し、幅30mm以上の粘着テープで1.5m以下の間隔で固定する。
 平形保護層配線は、とても薄い電線をタイルカーペットの下に配線する工事のことです。
平形保護層配線は、とても薄い電線をタイルカーペットの下に配線する工事のことです。ケーブルラックの敷設
アルミ製ケーブルラックは、支持物との間に異種金属接触による腐食を起こさないように取付ける。
架空配線
有線電気通信法に準じて、道路や鉄道の建築限界、建物や電線等との適切な離隔距離を確保する。
機器端子との接続
端子板への接続は、出側を右側とする。
端子盤内の配線処理
・端子盤内の配線は、電線などを一括に整然と行い、くし形編出しして端子に接続する。
配管工事の施工管理上の留意点

電気通信工事・電気工事において「配管」は、電線やケーブルを適切に収納し、保護するために欠かせない材料です。ここでは配管工事の主な施工管理上の留意点について配管の種類別に解説していきます。
配管の種類
金属管
文字通り金属製の配管のことで、乾燥、湿気、水気のあるような場所でも接続部に防湿・防水処理を施すことで制約を受けることなく敷設が可能なため、適用性が高い施工方法です。

VE管(硬質ビニル電線管)
可とう性がなくまっすぐの配管で主に屋外で使用される。熱加工で曲げることができる。「合成樹脂配管」という場合はVE管を指すことが多い。

PF管(合成樹脂可とう電線管)
可とう性があるしなやかにたわむ配管で、屋内ではPFS管、屋外ではPFD管といった使い分けが一般的で、グレーやベージュ色のものが多い。

CD管(合成樹脂可とう電線管)
可とう性があるしなやかにたわむ配管であるが、PF管よりも外径がほそく自己消火性や対候性がない。オレンジ色で安価。
HIVE管(耐衝撃性硬質ビニル管)
可とう性がなくまっすぐの配管でVE管よりも耐衝撃性能を高めた配管。
配管の施工管理上の留意点
金属管・合成樹脂配管/金属製電線管の露出施工
管の曲げ半径は管内径の6倍以上とし曲げ角度は90°を超えてはいけない。

波型硬質合成樹脂管(FEP管)の地中埋設
掘削した底盤は、充分に突き固めて平らかつ滑らかにする。
配管相互の接続
配管相互の接続は、適合するジョイントボックスまたはカップリングにより行う。
電線等の防火区画の貫通
金属管が貫通する場合、金属管と壁等の隙間に、モルタル、耐熱シール材等の不燃材料を充填する。

配管路の外壁貫通
屋内に水が浸入しないように管の先端を下向きにするなどの防水処理を行う。
コンクリートの穴開け(貫通口)
作業は、建造物損傷や作業中のはつり殻や埃の飛散など周囲に悪影響を及ぼさないように慎重に行う。
引込口の防水処理(架空引込み)
外部貫通部の電線管との間をモルタルで充填し、貫通部の配管は貫通部より建屋の内部を高く傾斜させ水の侵入を防ぐ。
引込口の防水処理(地中引込み)
水切りつばは、点溶接ではなく全周溶接とし、スリーブ・防水鋳鉄管(ちゅうてっかん)の水勾配は外下りとする。
地中埋設配管
・掘削した底部は、充分に突き固め平に滑らかにする。
・埋め戻し土砂は、配管に損傷を与えないように小石などを含めず隙間がないように突き固める。
・配管路には、地表と配管のほぼ中間に「埋設標識シート」を設ける。
・地中配管終了後、マンドリルにより通過試験を行う。
・FEP管(エフレックス/地中埋設配管用の保護管)では接続部で双方のパイロットワイヤを接続する。
・ハンドホール工事の掘削幅は最小幅とし、ハンドホールにFEP管を敷設する場合は、壁穴とFEP管のすき間にモルタルを充填する。
・ハンドホールに配管した後の埋め戻しは、土や砂を1層の仕上げ厚さが0.3m以下になるように締め固める。(掘削土をすべて埋め戻してから締め固めるのではない)
適切な配線・配管の施工管理は、安全性や耐久性の確保だけでなく、施工後の保守・点検のしやすさにも大きく影響します。計画的な施工と確実な管理を徹底し、高品質な工事を実現することが求められます。試験対策としては、基準や手順を理解するだけでなく、実際の施工現場をイメージしながら学ぶことが重要です。確かな知識と実践力を身につけ、信頼される技術者として成長していきましょう!
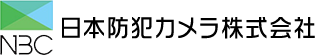
 03-6264-2138
03-6264-2138