トピックス
-
2025.9.11(最終更新日:2025.10.12)
<施工管理>活線作業・停電作業における感電災害防止対策

電気工事の現場では、設備の運用を止めずに行う「活線作業」や、計画的に電源を遮断して行う「停電作業」が避けられない場面が数多く存在します。しかし、電気は目に見えず、わずかな不注意が重大な感電災害へと直結することから、常に高い安全意識と入念な準備が求められます。
ここでは、こうした作業を安全に遂行するために欠かせない感電防止の基本的な考え方と、実践すべき対策について整理します。活線作業
活線作業(かっせんさぎょう)とは、電気が流れている「活線(生きている線)」の状態のまま、電気設備や電線路の点検・補修・清掃などを行う作業のことです。電力供給を継続できるメリットがある一方、感電のリスクが伴うため、絶縁用保護具や活線作業用器具を使い、労働安全衛生規則などの厳格な手順を守って行う必要がある、とされています。
対策まとめ
●絶縁用保護具の使用
●絶縁用工具の使用
●活線部を絶縁シートで被う
●活線部の周知留意すべき危険性①
配電盤の一次母線が活線であり、その二次側に入線、結線する作業において、盤内の照度が低く、手元の視認性が悪いことから、近接している一次母線に手や工具を接触する恐れがあるため、作業者の感電災害が発生する危険性に留意する。感電災害防止のための対策①
作業前に盤室に仮設照明を設置し、視認性を確保するとともに、活線部を絶縁シートで覆い、さらに一次母線が活線であることを作業者全員へ周知する。作業者には絶縁手袋と絶縁工具を確実に着用させ、感電災害を防止する。
留意すべき危険性①
既設受変電設備改修工事において、手元のケーブル結線作業に集中していた作業員が、狭い盤室で姿勢を変えた際、背後にある活線の分電盤に背中が触れる恐れがあるため、作業員の感電災害防止に留意する。
感電災害防止のための対策①
作業開始前に分電盤の活線部へ「活線注意」と明示し、TBMで活線部の危険性を周知する。さらに、作業員には、長袖作業着の他、電気用ゴム手袋、電気用ゴム長靴、電気保護帽等の絶縁保護具を着用させ、感電災害を防止する。
停電作業
停電作業とは、電気の供給を一時的に止め、停電させた状態で、電気設備の点検、修理、改修などを行う作業のことです。これは、電気が通った状態で行う活線作業と対をなし、電気工事や作業における安全を確保するための基本的な方法です。作業の安全のため、開閉器の施錠や通電禁止札の掲示、監視人の配置、そして残留電荷の放電などの措置が講じられます。
対策まとめ
●検電器による停電確認
●停電・通電範囲の周知
●ブレーカの遮断留意すべき危険性①
作業エリアが600㎡と広く、2日間に分けて実施する照明器具交換工事において、複数の作業班が混在し、当日の作業範囲を取り違えて通電中の配線を誤って切断する恐れがあるため、感電災害が発生する危険性に留意する。感電災害防止のための対策①
作業開始前のTBMで全作業員に停電範囲を周知し、交換対象の照明器具には赤色テープで印を付ける。作業前には検電器で停電を確認し、通電中の回路に誤って触れないように周知し、感電災害を防止する。検電器とは
電線や電気機器に電圧がかかっているかどうかを調べるための測定器です。電気工事やメンテナンス作業を行う際、感電事故を防ぐための安全確認に用いられます。
留意すべき危険性②
無停電電源装置(UPS)が接続された照明器具交換工事において、供給電源を切断してもUPSが自動でバッテリ運転に切り替わり、照明器具に電気が供給され続けるため、UPSの機能を知らない作業員が停電していると思い込み、結線作業中に感電災害が発生する可能性に留意する。感電災害防止のための対策
作業開始前にTBMでUPSのバックアップ機能を周知し、UPS本体のの電源を切断し、分電盤のブレーカを遮断するよう教育するとともに、UPS出力端子を検電器で確認し、電圧がないことを確認してから結線作業を行い感電災害を防止する。
無停電電源装置(UPS)とは
停電や電圧の変動といった電源トラブル時に、内蔵バッテリーから安定した電力を供給し続けることで、接続されたコンピューターや重要機器を保護する装置です。UPSは、重要なデータを保護したり、機器が安全に停止するための時間を確保したりする役割を担います。電動工具を用いた作業
電動工具を使用した作業時は、感電、刃や材料の跳ね飛び、巻き込み事故、振動障害、切創などの危険性があります。安全対策のために、適切な防護具の着用(防じんマスク、保護メガネ、手袋など)、材料の固定、工具の点検、取扱説明書の確認が不可欠です。
対策まとめ
●点検表により点検する
●使用許可シールを貼る
●絶縁抵抗値、アースの確認
●動作確認テスト留意すべき危険性①
屋外に防雨型コンセントを新設するための100V配線工事において、湿気の多い場所で電動ドリルを使用する際、工具の電源ケーブルやコンセントブラグの絶縁部の劣化による作業者の感電災害が発生する危険性に留意する。感電災害防止のための対策①
作業前に、電源ケーブルの被膜裂傷やコネクターの破損、スイッチの動作等を点検表により点検し、異常がなければ使用許可シールを貼る。これにより、安全が確認された工具のみを使用させ、感電災害を防止する。
感電災害防止のための対策②
作業前に使用する電動ドリルを、メガーで絶縁抵抗測定を行い、低圧規定値である0.1MΩ以上であることを確認した。さらに、アース接続をし、動作確認テストを実施することで感電災害を防止した。メガーとは
ケーブルや電気機器の絶縁抵抗を測定する計測器です。電気回路が外部に漏れず、安全が確保されているか(絶縁状態)を診断します。絶縁抵抗の単位はMΩで、値が大きいほど電気は流れにくく、良好な絶縁状態を示します。電気設備技術基準では、回路の電圧によって定められた基準値(例:100V回路で0.1MΩ以上)を満たすことが求められます。
活線・停電を問わず、感電災害は「ヒューマンエラー」「準備不足」「安全意識の低下」といった小さな油断から発生します。作業前のリスク評価、適切な保護具の使用、確実な検電・接地といった基本動作の一つひとつを丁寧に積み重ねることこそが、最大の安全対策です。
電気の特性を正しく理解し、常に“安全第一”の姿勢を徹底することが、現場と作業者を守る最善の方法であると言えるでしょう。
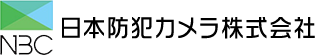
 03-6264-2138
03-6264-2138







