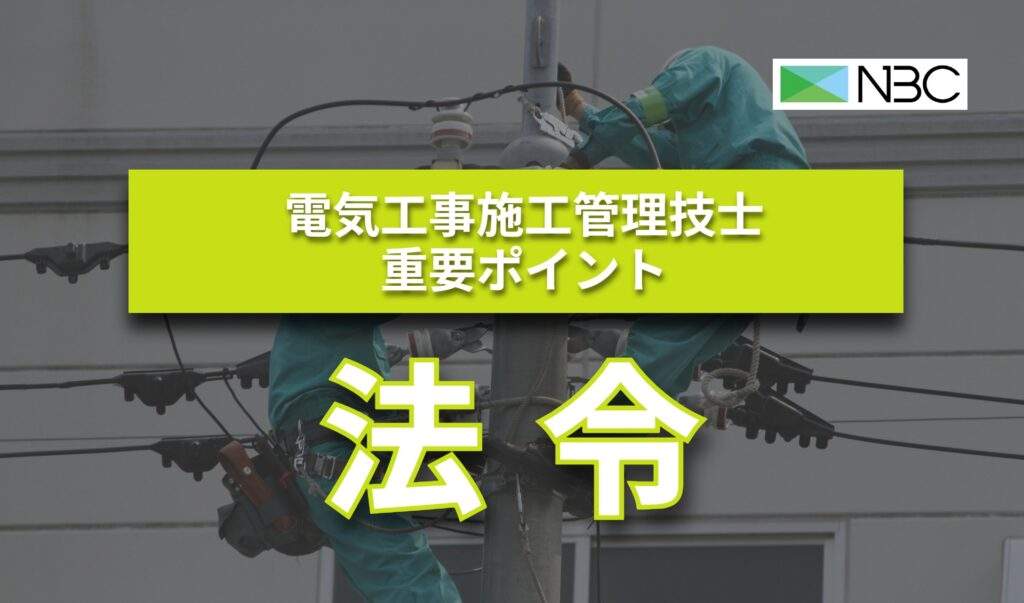トピックス
-
2025.9.8(最終更新日:2025.10.29)
<施工管理>施工管理技士が理解するべき”法令”

建設現場の安全と品質を守るためには、技術力だけでなく、法令の理解が欠かせません。
施工管理技士試験でも、「建設業許可」「労働安全衛生法」「電気工事士法」などの関連法規は毎年のように出題される重要分野です。これらは、現場の実務に直結する“基礎知識”であり、法令趣旨を正しく理解しておくことで、日常業務の判断力も大きく向上します。
本コラムでは、試験で頻出するこれら3つの法律について、出題傾向や押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。建設業法
建設業法とは、建設業を営む企業の質を向上させ、工事請負契約を適正化し、建設工事の適正な施工を確保するための法律です。建設業の健全な発展を促し、発注者や下請け業者を保護することで、最終的に公共の福祉に貢献することを目的としています。
第一条 (目的)
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。第三条 (建設業の許可)
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。第十八条 (建設工事の請負契約の原則)
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。第十九条の二 (現場代理人の選任等に関する通知)
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。第二十条 (建設工事の見積り等)
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。第二十二条 (一括下請負の禁止)
建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。第二十三条 (下請負人の変更請求)
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。第二十四条 (請負契約とみなす場合)
委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。第二十四条の二 (下請負人の意見の聴取)
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。第二十四条の三 (下請代金の支払)
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつできる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分にっいては、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。第二十四条の四 (検査及び引渡し)
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。第二十四条の八 (施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。第二十六条 (主任技術者及び監理技術者の設置等)
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をっかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものにっいては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。第二十六条の四 (主任技術者及び監理技術者の職務等)
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。労働安全衛生法
労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的とした法律です。具体的には、労働災害を防止するための基準の確立、事業者の責任体制の明確化、そして労働者の自主的な安全衛生活動の促進などを定めています。
第一条 (目的)
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。第三条 (事業者等の責務)
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
4 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。第十条 (総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの第十四条 (作業主任者)
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。第三十条 (特定元方事業者等の講ずべき措置)
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項第五十九条 (安全衛生教育)
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。第六十条 (職長教育)
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
第六十一条 (就業制限)
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。電気工事士法
第一条 (目的)
この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。第三条 (電気工事士等)
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。第四条 (電気工事士免状)
電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者第四条の三(第一種電気工事士の講習)
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。第五条 (電気工事士等の義務)
電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模事業用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)又は自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
建設業を支えるのは、確かな技術と法令遵守の姿勢です。
施工管理技士試験で出題される建設業法・労働安全衛生法・電気工事士法は、その基本を確認するための重要な指針といえます。
一つひとつの条文の意味を理解し、現場で活かせる知識として身につけることこそが、真の「施工管理力」を高める第一歩です。
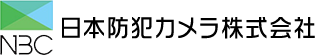
 03-6264-2138
03-6264-2138